- 自分の時間がほしい
- 何度も同じ話をされるのがストレス
- 自分の人生に集中したい。なぜ私だけが・・・
- 小さくよたよた歩く親の姿をみると重く感じている自分を責める
- 寂しそうにしている親をみると可哀そうに感じてしまう
- どうしたら重たさを感じずに、親と一緒に生活できるの?
親が高齢になり、その姿をみてイライラして冷たくしてしまう。「老化現象だから仕方ない」「寄り添う声掛けをしなくてはいけない」とわかっていても毎日顔を合わせていれば、優しく出来ない人は多いでしょう。そんな自分を責めて辛くなり、そのうちに親を憎んでしまう。そうならない為に、親との距離を置くことが大切です。でも同居や近くに住んでいたらどうやって距離をとったらよいのでしょう・・・
本記事は同居、あるいは近所に住んでいる高齢者の親に優しく接したいと悩んでいるあなたへ距離の取り方を解説しています。
私も自分の母親(77歳)と同居しています。結論からいうとイライラやストレスがなくなることはありません。完全にストレスがなくなることを目指すのではなく「どう付き合っていくか」を見つけていくことが大切です。自分を犠牲にしすぎると、結局心に余裕がなくなり、関係が悪化してしまします。自分を大切にすることが、結果的に親のためにもなります。
親に優しくできない心理、親との距離の取り方についてまとめた別記事「高齢者の親にやさしくしたい、でもできない」で詳しく解説しています。リンクを貼っておきますのでよかったら参考にしてください。☟
- 「介護を自分でする」と間違った覚悟をしない。
- 「親には親の生き方がある。」と理解する。
- 視点や、伝える言葉を変えることが我慢しているようで実は自分が楽になる。
【高齢者の親と同居】イライラする5つの理由
同居していれば、嫌でも親の様子が毎日目に入ります。離れていれば見えないところもあるので、少し寛大に捉えられるけど、毎日一緒にいると些細なことも、積み重なれば大きなストレスになります。加齢が原因だとわかっていても許せない気持ちは湧いてきます。
高齢になった親にイライラする主な原因を挙げてみます。
- 生活リズムや価値観の違い
- 何かと干渉してくる、プライバシーが確保できない
- 弱っていく親の代わりに、やることが増える
- 何度も同じ話を聞かされる
- だらしがなくなった姿を目の当たりにする
生活リズムや価値観の違い
生活リズムや価値観の違いは世代によってどうしても生まれるものです。いくつか例を挙げてみます。
生活リズムの違い
- 就寝時間について、親は早寝早起きで朝早くから活動を始める一方で、子どもは仕事などで夜型。朝は少しでも寝ていたい。時間帯のずれによる生活音がお互いの睡眠の妨げになる。
- 食事について、親は決まった時間に食べたがるが、子どもは仕事の都合などで不規則になりがち。親に合わせなければとストレスになる。
- 親は1日中テレビやラジオをつけっぱなしにする。番組の好みも親と子で違う。また、耳が遠いことから大音量で聴いていて、耳障りに感じる。
価値観の違い
- 親は近所付き合いや、親戚関係を重要視する。人間関係の濃さや付き合い方に対する考え方の違いがある。
- 加齢とともに、必要なものとそうでないものの区別がつきにくくなり、子どもが整理整頓をしようとしても、物を手放すことに抵抗を感じ、捨てられないため家の中が片付かない。
何かと干渉してくる。プライバシーが確保できない
生活を共にすると、どうしても口を挟まれることが増え、干渉が気になります。
高齢になると何かと自分のタイミングで踏み込んでくることが多くなります。子どもの方は仕事で疲れて帰ってきてやっと一息つけると思ったら、親から色々と頼まれる、愚痴を聞かされるなどで、うんざりすることがあります。
また、孫にたいしてもいつまでも幼い感覚が抜けず、接し方について「親なんだからこれくらいはしてあげないと可哀そう」学校や勤めに向うときも「送り出さないの?」「心配じゃないの?」などまるでダメな親のような発言をされることもあります。
弱っていく親の代わりに、やることが増える
親が高齢になりできないことが増えてきて、やることが増えてきます。そうすると自分の大切な時間が削られていき、理不尽に感じてしまいます。
食器などの洗い物の汚れが落ちていない、洗濯物がシワくちゃのまま干されているなど、二度手間になりイライラします。また、親あてに郵送された書類関係も読んでもわからないからと、封を開けずに渡されると甘えられているように感じ、怒りがこみ上げてきます。
何度も同じ話を聞かされる
何度も同じ話をするのは、老化現象で仕方がないとわかっていても、同居(近所)していれば日常的に聞かされるため、イライラします。それがネガティブな内容や悪口だとなおさらです。親のプライドを傷つけてはいけないとわかっていても「何回も聞いたよ!」と話を途中で遮ってしまうことがあります。
だらしがなくなった姿を目の当たりにする
一日中ゴロゴロしてテレビをみて過ごしていたり、掃除をしない、身なりに気を使わないなど、だらしない姿をみてがっかりします。そうした親を受け入れられず、しっかりしてほしいと思います。また、運動しないと筋力が落ちてしまう、痴呆が進むなどの心配からイライラしてしまいます。
【高齢者の親と同居】距離を置く7つの方法
いつでもどこかで考えている親の事。このような心理状態が続くのは精神的に辛いものです。同居していれば「自分がしなければ」という気持ちも強くなります。親子の関係はいつか「面倒を見る側」と「面倒を見てもらう側」が入れ替わります。そのことを受け入れて、あなたの気持ちが楽になるように以下の7つの方法を紹介します。しかし、すぐにすべて親の事を理解し受け止める必要はありません。同居してしていればイライラするのは当然の事。徐々にできることから始めましょう。
- 親と対話をする
- 行動の裏側にある目的を理解する。
- 加齢のためやりたくてもできないと理解する
- 出来ていることに目を向けて、親に伝える
- 「この時間はこれをするから」と宣言する
- 公的サービスを利用して離れる時間をつくる
- 親と距離を取ることに罪悪感を持たない
親と対話をする
対話をする理由は【距離はお互いに1人の人間】という理解をする為です。
会話を繰り返すのは親の願いや生きがいを理解し、「親には親の生き方がある。」という受け止めをするプロセスです。
子どもは自分が安心する為に、親の生活を管理しがちになります。しかし、自分が親のやりたいことを全て叶えることはできませんし、しようとすればやりきれず疲弊して親を憎みはじめます。だとしたら関わるのではなくて、色々な人の手を借りながら親が好きな事をやれている方がいいだろうという考え方にシフトしやすいのです。
親も子どもに負担をかけず、気を使わずに支援を受けて自分のやりたいことを続けて行くという考え方に気づきやすくなります。
対話をする目的
親の今後の生活に対してのイメージや希望、思いを共有する為に対話が大切です。
親が何を大切にしていこうとしているのかがわかると安心、安全に走らなくてもすみ、子ども側の不安感が相当下がるそうです。
親の希望がわからないからどうすればいいのかわからなくなって、とにかく安心、安全に考えが走り「転びそうだから早く老人ホームに入れちゃえ」とか考えてしまいます。
高齢の方にとって転びそうだからなんてさして大事なことではありません。自分から施設に入りたいなんて思う人はほとんどいません。
「転ぶかもしれないから自分の足で馬券買いに行くのやめようかな」と思うお父さんはいません。転ぶかもしれないけどお父さんは今日歩いて馬券を買いに行きたい。
その理解がないと「転ぶと危ないからネットで買えばいい、その方が安全」と子どもは言い出します。
しかし対話をしておく事で何を目的としているのかがわかってきて、間違った方向に行かなくなります。
「お父さんは馬で金儲けしたいんじゃなくて街中を歩きながら知り合いと挨拶して帰りに喫茶店に寄るのが楽しみなんだ」と理解できます。
引用著書:「親不孝介護」 著者:山中浩之/川内潤
お父さん、お母さんの役目以外に一人の人間としての生き方があります。その事を尊重できる心構えをしましょう。
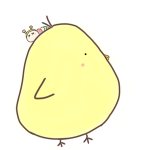
健康でいて!歩けるように足を鍛えて!認知症にならないでね!というのは子供側の理屈なんだね・・・
行動の裏側にある目的を理解する。
親のやることが頑固に感じることがあります。しかしその裏側には何かしらの理由があります。アドラー心理学で目的論というのがあります。言動の裏側にある目的を知ることで、それまで感じていたストレスが緩和されていくことがあります。
人の行動は性格や何かしらの原因から起こるのではなく「こうしたい」という目的から起こるというものです。
同居している90歳の父親がお箸を使いにくそうにしていることに気付き、「スプーンを使いなよ」と息子さんは数回父親に伝えたが、「いらん」と言います。親切に言っているのにとなんだその態度はと思いましたが、時間をおいて「父はなぜ使いにくい箸を使おうとしたのか?」と考えたそうです。そうして出た答えは「色々できないことが増えている中で数少ないできることはやりたい」ということでした。
引用≫https://esse-online.jp/articles/-/24355 「高齢父の言動」が年々ストレスに…。お互いの関係性がラクになる接し方
👆とても参考になる内容でした。ぜひ読んでみて下さい。
「頑固なんだから」「ひねくれて」と思いがちですが、親もちゃんと理由があり、ある意味自分と戦っている気がします。

何も理解していないときはなんでだろうとイライラしますが、目的がわかると心から納得できます。
やりたくてもできないと理解し、出来そうなことはお願いしてみる。
親は一生懸命やっていても下記のような状況をみると子どもは手を抜いているように感じてしまうことがあります。
- 目が悪くなってきている為、食べこぼしたことに気が付かない、掃除がすみずみまで行き届かない
- 手を伸ばして頭より、上の作業する動作は高齢者には労力を要し、洗濯物の干し方が雑になる
- 身体や頭の洗い方が雑になる。家族は加齢臭が気になりだす。
- ゴミ出しは高齢者にとって重労働。特に生ごみや重いごみの運搬が困難。部屋にゴミが溜まってくる。
「やりたくても、出来ない」ことを理解すると、自分の気持ちが楽になります。その中で、できそうな事をお願いしてみましょう。
親はやらないのではなくて、できないこともあります。子どもの方はうまくいかないことを目にすることが多くなり「このくらいは、できるだろう。なぜやらないの?」と思うことがあります。今まで出来ていたことが徐々にできなくなる過程で親の事をだらしがないと思い始めてしまいます。
出来る限り親は自分でやろうとしているけど、うまくできない。口には出さないけど傷ついているときは沢山あるはずです。出来そうなことをやってもらい、「ありがとう、助かったよ」と伝えると親もよろこび良い関係が築けます。

私の母は長時間立っていることが辛いので、座ってできるさやえんどうの筋とりや、ねぎの皮むきなどをやってもらいます。
出来ていることに目を向けて親に伝える。
同居しているとどうしてもできない事ばかりに目が行きます。私自身もそうです。洗濯物の干し方、掃除などすべてが気に入らなくなって、文句ばかり言っていました。でも良く考えると出来ている事や、良いところが見つかります。しかし、これは意識しないと中々見えません。
私の母は膝と腰が悪く、毎日痛そうです。でも毎日明るく、機嫌良く生活しています。私なら、家族に八つ当たりするかもしれないと思うと「凄いなぁ」と気が付く事が出来ました。
そして、「お母さんは凄いね。痛いところがあるのに八つ当たりせずに、毎日穏やかに過ごせて。私なら痛くて不機嫌になる日もあるかもしれない」と伝えると、とっても嬉しそうでした。
良い面に気付き認め、伝える事で何より自分の気持ちが楽になりました。
「この時間はこれをするから」と宣言する
自分の時間を作ることは、自分の心を守るためにもとっても大切です。
同居していると、何かをしようとしているときによばれたり、楽しみにしていたドラマをゆっくり観ていると、話しかけてきたり、自分の時間が思うように取れないときがあります。それが重なると「なんで私ばっかり・・・」と辛くなり、ストレスが溜まります。
そんな時は「この時間は〇〇をするね」とはっきり伝え、可能であれば別の部屋に行きましょう。
- 今から1時間仕事に集中したいから用事はそのあとでね。
- 体調がすぐれないから(嘘でもいいと思います)少し横になるね。
1人の時間をとることに罪悪感を感じるかもしれませんが、ストレスを発散させて、親に少しでも穏やかに接するためには必要なこと。自分の為、親の為と割り切りましょう。
私もはっきり伝えるようにしています。最初は「邪魔にして!」なんて思われるかな?と心配したけど思い切って伝えると理解してくれ、自分の時間が確保できるようになりました。嘘も方便。生き詰まった時には「読みたい本があるから図書館に行って読んでくる。だから少し遅くなるよ」(嘘)など理由をつけて出かけることもあります。その他に、時々仕事に行くふりをして映画をみたり、カフェで読書することもあります。うしろめたい気持ちもありましたが頑張っている自分へのご褒美です!

私は自分を責めない為に、月に1回一緒に外出をして気分転換するという、小さな習慣を作りました。行き先も自分の好きな日帰り温泉が多いです。そうすることで心のバランスをとれるようになりました。普段しっかり体を洗ってない母も温泉ではしっかり洗ってくれ一石二鳥です。
公的サービスを利用して離れる時間をつくる
「ずっと一緒にいるのがしんどい」「一人の時間がほしい」と思っていても、同居していれば「自分が頑張ればいい」「誰かに頼るのは、申し訳ない」と思いがちです。しかし公的な介護サービスや支援制度は、あなたのような頑張っている人が「無理をしすぎないため」に利用するべきサービスです。
「手を抜く」のではなく「上手に手を借りる」。それは、長く続く同居生活の中でとても大切な視点です。公的サービスを利用することで親との関係にも少しゆとりが生まれます。一人で抱え込まず、利用できるものは利用して、あなた自身の人生も大切にしましょう。
実体験として、娘と距離を置いた記事を書いています。距離を置くことでお互いが良い方向へ、進むことができました。ぜひ読んでください。
親と距離を取ることに罪悪感を持たない
高齢化社会を迎え、介護制度を使って支えあう世の中ですが、親と適切な距離をとろうとすると、第三者から「親不孝」と言われることもあるかもしれません。しかし、ひと昔前とは家族の形が変わっています。昔は家族で面倒を見るしかなかった時代の習慣が「親のそばにいなさい」と強制してくることがあります。同居していたり、近くに住んでいると、人に任せるということに罪悪感を感じてしまいがちですが、自分が少しでも楽にならなければ、親も子も苦しくなります。
同居(近所)している3つのリスク
同居は高齢者にとってメリットが大きいように感じますが、実は下記のようなリスクもあります。これは実際に感じるところがあります。私の母も自分で考えようとせず、どんどんと私頼りになっている危機感があります。
- 介護を自分でやると覚悟してしまう
- 親との関係が悪化する
- 親を孤立させてしまう
介護を自分でやると覚悟してしまう
「介護を自分でやる」これは、離職や家庭崩壊にもつなりかねない本当に危険な考え方です。なぜなら介護サービスを利用しないで頑張ってしまうからです。
親も子どもも同居していたり、近くに住んでいることで「すぐに何とかしてあげれる、気が付ける」と安心してしまう、あるいは「同居(近所)しているから自分がやるべきなんだろう」と子どもの方が、覚悟を決めてしまう事があります。しかしそれは大きな誤解なんだと、介護が始まる前に気づいて、適切な距離が保てるように介護支援サービスを頼ろうと、気持ちの準備をしましょう。
参考著書:「親不孝介護」 著者:山中浩之/川内潤
親との関係が悪化する
例えば親が近所に住んでいるから会社帰りにちょくちょく寄ったりしていると、親の方も子どもが来る日まで自分でやれるところまでやらずに待っているようになります。
優しいあなたは弱ってきた親の面倒をつい見たくなりますが「自分だけでは全て対応できない」こともはっきり示しておかないと親はあなたを頼りきりになります。
子どもが手伝ってくれるから「うちは生活できているから大丈夫」と、支援を受けるチャンスを断ったしまったり、受けようとも思わなくなってしまいます。
子どもも「親をたすける」という役割が当たり前のことと思い、親が困っていることに手を貸しますがだんだん親の体調や、精神状態が悪化してくると無理がたまっていき「会社を休んできているのに家がまったく片付かない」「自分の時間を犠牲にしているのに」とイライラして怒ってしまいます。親の方は「子どもがきても機嫌が悪く怒ってばかり」となって子どもの顔色をうかがったりと、お互いの関係が悪化してしまいます。
参考著書:「親不孝介護」 著者:山中浩之/川内潤
親を孤立させてしまう
いつでも手を出してしまうと親の方は「子どもがやってくれる」と思い介護保険や外部サービスに頼ろうとしないことでだんだん親を孤立させてしまいます。
家族が直接親を支援しやすい状態というのは、介護にとってはリスクであるということをしっかり理解することが大事です。
「外部に相談する」という発想を親に持ってもらうには「本人に困ってもらう」ことです。「困ったな、でも子どもは来れないしどうしよう?」そこで嫌だけど包括に相談しようという考えに変わってくる状況を作ります。
参考著書:「親不孝介護」 著者:山中浩之/川内潤
ご家族のテレビの大音量でお悩みの方へまとめ
- 同居や近隣に住んでいる事を親が困った時にすぐに手を出せるから何とかなると好条件に捉えがちだが、実は距離が取れないという悪条件である。
- 「介護を自分でする」と間違った覚悟を子どもの方がしてしまいがちだが、それは大きな誤解なんだと介護が始まる前に気づいて気持ちの準備をする事が大事。
- 外部に相談する意識を持ってもらうには親に困ってもらう。
- やるべき事は親との対話。親が生活の中で何を大事にしていこうとしているのか、何を大事にしているのかがわかると子ども側の不安感が相当下がる。
- お父さん、お母さんである前に一人の人間であることを理解する。
物理的な距離をとることが親も一人の人間であること、自分もまた尊重すべき個人と気づくために大切です。距離が近すぎて手を出しすぎてイライラしていずれ親を憎み関係が壊れるより、外部のサービスを利用しながらお互いがいい関係でいられること、親を個人として大切にすることが本当の親孝行ではないでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。私自身高齢の母と同居している中で「何で、私の邪魔ばかりするの?」「1日中家にいるのに何で片付けてくれないの?」休日は母の食事の準備を三度三度準備し、子どものようにごはんを待っている母の姿に、言いようのない憎しみが湧いてくることもありました。もちろんすべてを受け入れることはできず、いまでも葛藤はあります。しかし親子のバランスが入れ替わった事、親も一人の人間であり価値観が違うこと、頼りたい気持ちを少しずつ諦めたことで気持ちが楽になってきました。そして介護が始まる前に気づいて、適切な距離が保てるように介護支援サービスを頼ろうと、気持ちの準備もできました。この記事を読んで少しでも気持ちが楽になってくれたらこんなに嬉しいことはありません。
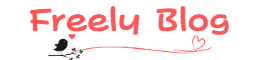







コメント